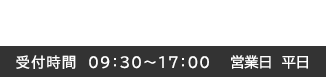NEXTi
LAW & ACCOUNTING FIRM
NEXTi法律会計事務所は弁護士と税理士により東京都港区赤坂に設立され、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。
依頼者の悩みに寄り添えるパートナーとなれるよう心がけ、親切丁寧にサポートいたします。
NEXTi法律会計事務所は弁護士と税理士により東京都港区赤坂に設立され、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。
依頼者の悩みに寄り添えるパートナーとなれるよう心がけ、親切丁寧にサポートいたします。
わたしたちはクライアントの
未来(NEXT)のために
いつでも対話を大事にし(i:interactive)
お客様の発展のために革新的に(i:innovation)
柔軟な発想で(i:imagination)
貢献いたします。

NEXTi法律会計事務所は、法務及び会計・税務に関する総合的なアドバイスをワンストップにてご提供いたします。